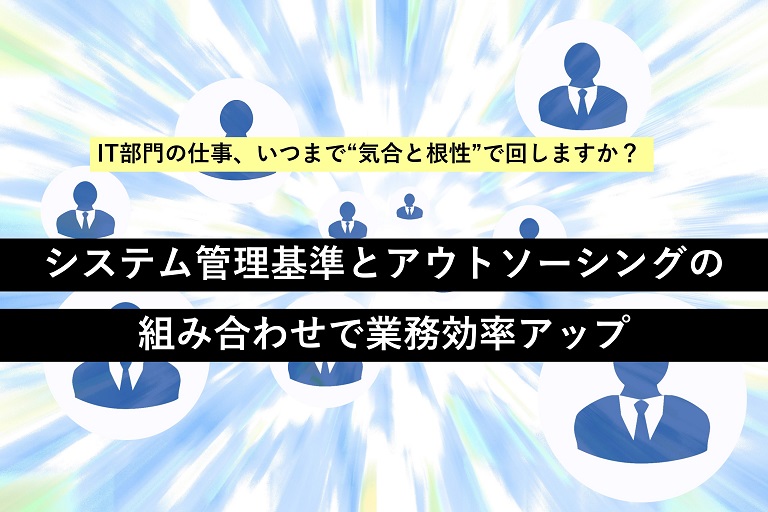
クラウド対応、ゼロトラスト、働き方の多様化…情報システム部門が抱える業務は年々増える一方。
「このままでは回らない」と感じながらも、手が打てないまま日々の運用に追われていませんか?
本記事では、そうした課題に対して実践的かつ効果的なアプローチである、「システム管理基準 × アウトソーシング」の組み合わせを紹介します。
現場での実例とともに、IT部門の中間管理職が押さえておくべき導入のステップを解説します。
目次
電話対応サポートの重要性と背景
近年、デジタル化の進展とともに、企業における顧客対応や社内サポートの在り方が大きく変わりつつあります。チャットボットやメール対応といった非対面のサポート手段が増える中で、いまだに「電話対応」が担う役割は小さくありません。むしろ、迅速で確実なコミュニケーション手段として、重要性が再認識されています。
たとえば、緊急時やトラブル発生時には、メールでは対応が間に合わないこともあります。そんなとき、即時に状況を把握できる電話対応が信頼のカギを握ります。また、顧客にとっても、話しながら解決していく電話サポートは安心感を与えるため、企業への信頼にも直結します。
DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代において、電話対応は単なる旧来型の手段ではなく、「声の温度」を通じて信頼を築くための手段へと変化しています。そのため、企業は電話対応の品質を重視し、それにふさわしい体制を整える必要があります。
特に、IT関連のサポートやBtoB企業においては、専門的な知識や迅速な判断が求められるため、誰でも対応できるわけではありません。ここで重要になるのが「ヘルプデスク」や「コールセンター」といった、専門性を備えたサポート組織です。
どちらの体制を選ぶかによって、対応品質や顧客満足度、さらには業務全体の効率にも影響を与えるため、しっかりと違いを正しく理解したうえで、自社に適した選択を行うことが必要です。
この記事では、ヘルプデスクとコールセンターの違いを明確にし、それぞれの強みや導入のポイント、そして組み合わせによる可能性までを丁寧に解説していきます。電話対応の質を高めたい、サポート体制を見直したいという方は、ぜひ参考にしてください。
IT関連での ヘルプデスクとは?
ヘルプデスクとは、主に社内の従業員や特定のパートナー企業を対象に、IT関連のトラブルや技術的な課題を解決するためのサポート窓口です。企業のIT部門の一部として設置されることが多く、「社内ITの困りごとを解決する専門部隊」ともいえる存在です。
たとえば、「パソコンが立ち上がらない」「社内システムにアクセスできない」「ソフトウェアの設定が分からない」といった問い合わせが寄せられた際に、原因を切り分けて迅速に対応します。よって、業務の停滞を最小限に抑え、従業員の生産性を維持する役割を担っています。
ヘルプデスクに求められるのは、まず第一にITに関する幅広い知識です。ハードウェアやソフトウェアの基本的な仕組みはもちろん、ネットワークやセキュリティ、クラウドサービスなどに関する理解も必要となります。また、複雑な問題に対して冷静に対応し、状況を正確に把握・分析するスキルも不可欠です。
また、社内ユーザーとのコミュニケーション力も重要です。技術的な用語をかみ砕いて伝える力や、相手のレベルに合わせて説明できる柔軟性が求められます。ただ問題を解決するだけでなく、ユーザーにとっての「頼れる存在」として信頼を築く姿勢も不可欠です。
企業によっては、社内ヘルプデスクをアウトソーシングすることで、IT部門の負荷を軽減するケースも増えています。外部の専門業者に委託することで、24時間対応や全国サポート体制を実現できる点が魅力です。特に拠点が複数ある企業やリモートワークが広がっている組織では、こうしたアウトソースの導入が有効になります。
ヘルプデスクは単なるトラブル対応部門ではなく、企業のIT環境全体を支えるインフラ的な役割を果たしています。その役割の重要性を理解し、適切な運用体制を整えることが、業務効率や従業員満足度の向上につながります。
ヘルプデスクとコールセンターの違い
ヘルプデスクとコールセンターは、いずれも「電話による対応業務」を行うという点では共通していますが、その役割と目的、必要とされるスキルや知識には大きな違いがあります。まず対応範囲について、
ヘルプデスクは主にIT技術に関する専門的な問題解決を目的としており、利用者は社内の従業員や特定の取引先が中心です。利用シーンの観点から見ると、ヘルプデスクは例えば「パソコンが立ち上がらない」「ネットワークにつながらない」といった技術的なトラブルが発生した際に活躍します。ということで、トラブルシューティングに特化したサポート機能を担っています。担当者は、ITに関する専門知識や技術的なトラブル対応力が求められ、論理的思考や問題分析能力が重要になります。業務の成果指標は、解決までのスピードや正確性、エスカレーション率などが重視されます。
コールセンターは不特定多数の顧客を対象とし、商品やサービスに関する問い合わせ全般を受け付ける窓口として機能します。利用シーンの観点から見ると、「商品の納期を知りたい」「サービスに不満がある」といった、顧客の声に対応する場です。ということで、顧客接点を管理・強化するためのサービス機能を持っている、といえます。担当者は、顧客との対話を円滑に進めるためのコミュニケーション能力や、臨機応変な対応力、ストレス耐性などが求められます。業務の成果指標は、応答率や顧客満足度(CS)、通話時間、一次解決率などが主な評価軸となります。
このように、ヘルプデスクとコールセンターは見た目は似ていても、その本質はまったく異なるサポート体制です。自社の課題が「技術的な問題の迅速な解決」なのか、それとも「顧客満足度の向上」なのかによって、選ぶべきサービスは変わってきます。正確に違いを理解することが、最適なサービス導入の第一歩といえるでしょう。
自社に合ったサポート体制の選び方
ヘルプデスクとコールセンター、それぞれの役割や特徴を理解した上で、最終的に自社にとって最適なサポート体制をどう選ぶかが重要です。選定のポイントとしてまず押さえておきたいのは、自社がどのような課題を抱えており、何を目的としてサポート体制を導入するのかを明確にすることです。
例えば、社内のITトラブルの頻度が高く、それによって業務が滞っているのであれば、ヘルプデスクの導入が効果的です。一方で、商品・サービスの問い合わせ対応や顧客満足度の向上を重視するのであれば、コールセンターの設置・活用が適しているでしょう。近年では、これら両方の機能を兼ね備えたハイブリッド型のサポート体制を導入する企業も増えています。
このようなハイブリッド型の一例として注目されているのが、NDK日本電通の提供する「もしもしITサポート」です。このサービスは、企業のIT環境全体を見据えたサポート体制を構築し、ヘルプデスク機能による専門的なIT支援と、コールセンター機能によるユーザー対応を統合的に提供しています。特に、オンサイトを含む全国対応や24時間365日体制といった手厚いサポートが強みであり、社内のトラブル対応だけでなく、外部の取引先からの問い合わせにも柔軟に対応できます。
導入事例としては、リモートワークを本格導入したある中堅企業が「つなぐITサポート」を活用し、社内外からの問い合わせに一元的に対応できるようになったことで、従業員の生産性向上と顧客対応品質の向上を同時に実現したケースがあります。従来はIT部門が抱えていた対応業務の多くをアウトソーシングすることで、社内リソースをコア業務に集中できるようになり、業務効率化にも貢献しています。
最適なサポート体制を選ぶためには、単に「どちらが良いか」ではなく、自社の実情に応じた柔軟な発想が求められます。ヘルプデスクとコールセンターの特性を理解したうえで、必要に応じて組み合わせることで、より強固で効率的なサポート体制を築くことができるのです。
まとめ
ITや業務の複雑化に伴い、サポート体制の重要性はますます高まっています。ヘルプデスクとコールセンターは共に「問い合わせ対応」という共通点を持ちながらも、その目的や得意分野、必要なスキルは異なります。前者は技術的な問題を迅速に解決し、業務の継続性を支える存在であり、後者は顧客との接点を担い、ブランド体験を左右する重要な役割を果たします。
だからこそ、自社の業務内容や課題に応じて適切な体制を選び取ることが、業務効率化や顧客満足度の向上、さらには競争力強化につながります。また、ヘルプデスクとコールセンターの機能を組み合わせることで、より柔軟かつ効果的なサポート体制を構築することも可能です。
NDK日本電通の「もしもしITサポート」は、その両方のニーズを満たすハイブリッド型ソリューションとして、多くの企業から支持を集めています。ITサポートのアウトソーシングを検討する際には、こうした包括的なサービスの導入も視野に入れると良いでしょう。
今後のITサポート体制の選定において、本記事が自社に最適な判断を下す一助となれば幸いです。
